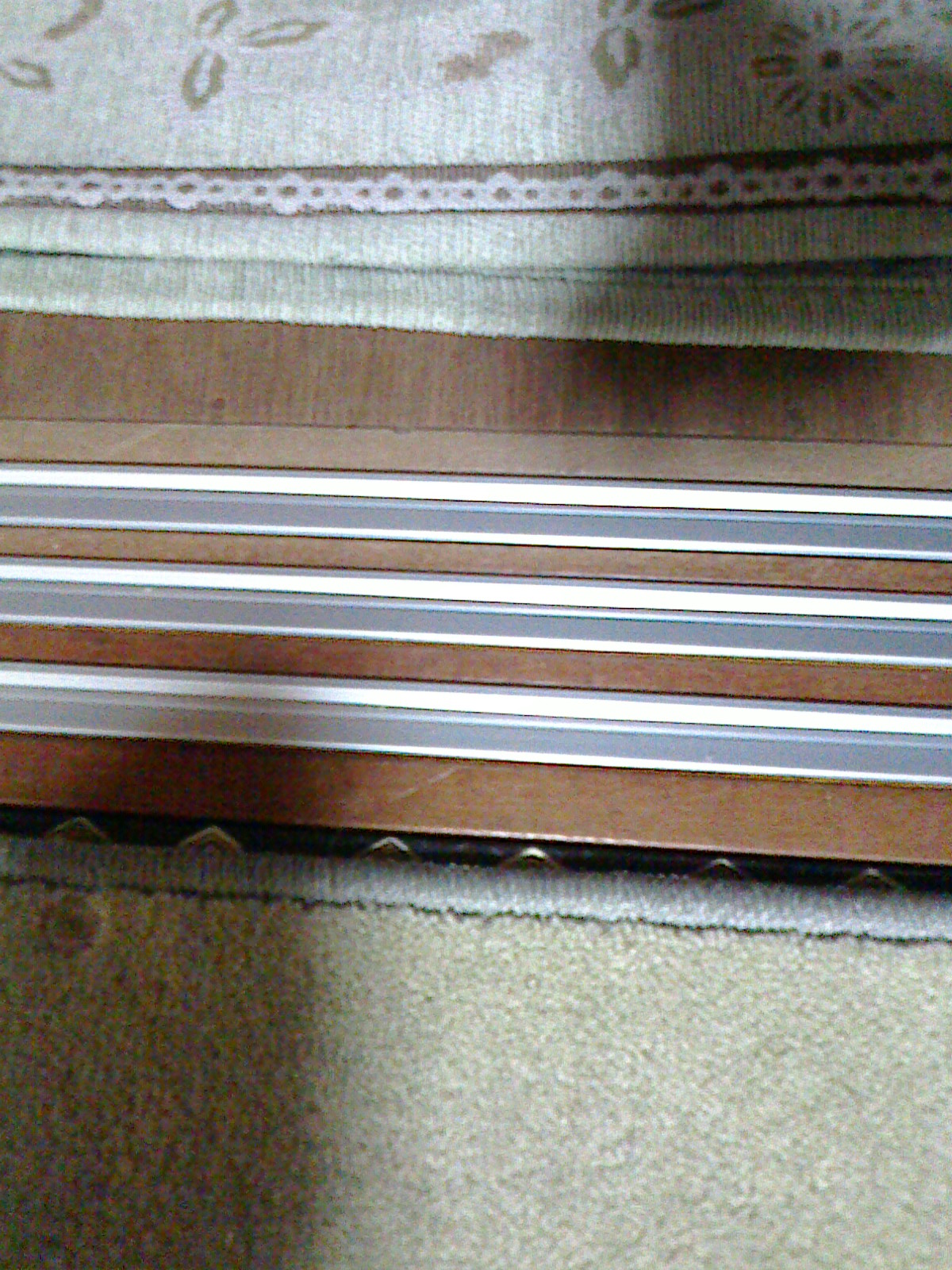柏尾建設は住む人へのやさしさを追求する健康住宅を目指します柏尾建設は住む人へのやさしさを追求する健康住宅を目指します |
||||
 こんにちは。大工の柏尾です。 今回は網戸の無い窓に網戸がつけられる話です。 今回使ったのは、OK組立アミドという商品です。 実はホームセンターにも売っている商品なので、 知っている方もいるかもしれません。 小、中、大の3種類の大きさがあり、網は別売りでした。 ただ、アルミを綺麗に切る事ができないと難しい商品で、 日曜大工で買ってきて作るのは大変そうでした。 網戸を自分で作れる、とは考えもしなかったので、これからは 網戸を作る提案もしていきたいと思います。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています

Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
 お疲れ様です。 大工の柏尾です。 今回の写真は、レンジフードの交換です。 取り替え前の写真を撮り忘れてしまっていますが、左右のピンクのパネルがレンジフードの上にもついていました。 スイッチが効かなくなったり、換気扇だけでも交換したいという方は、ここだけ交換なんかできるんだと知ってもらえれば幸いです。 今回から、タブレットからの投稿を頑張っていこうと思います。 短い文章になりますが、回数を去年より多く投稿していければなと思います。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
養父市 押入れのレールの入れ替え工事 こんにちは、大工の柏尾です。 今回の工事は、押入れのレールを変える工事です。 皆さんの押入れの戸は、ふすまでしょうか? ふすまの場合は敷居に溝が入れてあると思います。 場合によっては、写真のように”敷居すべり”という 滑りをよくするシートが貼ってあるかもしれません。 今回の工事は、この敷居にレールを入れ、ふすまに 車を取り付ける工事です。 レールは、敷居の深さほどの厚みで、うまいこと 入る大きさで設計してあります。 こちらはふすまの下側を写した写真です。 ”戸車”と呼ばれるタイヤをふすまに埋め込むのですが、 これが結構大変です。 小さな穴のようですが、ドリルで掘って、ノミを使って 深さを調整し、ミリ単位で加工します。 完成すると、動きすぎるほどよく動くようになり、 今までの力で閉めると、柱に扉が当たった時に大きな音が 出てしまうかもしれません。 難しい工事の割に、出来上がった後は普段、目にすることの 無い場所になりますが、軽く、使い勝手はよくなるので、 結構面白い仕事だと思いました。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
 養父市H様邸 納屋工事 こんにちは、大工の柏尾です。 今回の写真は、畑の一角に納屋を建てているものです。 小さくても屋根、壁は当然ありますし、扉も必要です。 よその畑の小さな納屋は、光が漏れる隙間がいくつもあったりして、「あんな小屋でも昔はきれいだったんかなぁ」とか、失礼なことを考えながら建てていました。 さて、この納屋と住宅との違いはなんでしょうか? 同じところを探す方が難しいかもしれませんが、まず床が無いことが大きいです。床を上げると、アプローチ部分である玄関や、手前の地面に工夫が必要です。階段状にするのか、スロープを作るのか、といった感じです。 次に大きなことは設備関係でしょうか? 電気もガスも水道も、ありません。どこかから引っ張ってこないといけません。満足に住むためには他にもとても多くの要求を満たす必要があります。 この納屋には必要がないため、すべて省いています。 少し考えてみるだけでも、住宅は人それぞれの要求に対し、その住宅ごとに形を変えて要求を満たしています。そして、その分、住宅にはより多くの手入れが必要になってきます。壁や床の張り替えもそうですが、設備関係は特に多くの費用が掛かります。 納屋は大抵のことを省いているため、維持費みたいなものはほぼかかりませんが、それでも大切に使うことでよその畑の隙間だらけの小屋のようになるのを少しは遅らせることができると思います。 納屋を見てこんなこと考えるのは田舎の建築屋くらいだろうなぁと思います。この納屋は、長持ちしますように。。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
養父市 H様邸 屋根工事 こんにちは。大工の柏尾です。 写真は玄関から隣の敷地までの渡り廊下のような屋根を付けた状態です。 材料は一般的に『ポリカの波板』と呼ばれるものを使っており、光を取り込み、雨をよけながら風を通すような形になっています。 ほとんどの屋根は、雨が溜まらないように斜めになっていますが、屋根を真上から見たときの形が四角でなくなると、途端に屋根を作ることが難しくなります。イメージが付きにくいかもしれませんが、たとえば敷地の境界線と建物の外壁が平行で無い時に、よく屋根を真上から見下ろした時の形が台形になり、とても難しくなります。 柱にしろ土台にしろ、大工さんの考える構造物は水平であり鉛直(水平に対して垂直)であることが大前提にあるので、階段や屋根など、斜めの形を作ることはとても難しいです。その高さ向きの収め方をきれいに収まった形にできる人は、優秀な人だと思います。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
養父市 S様邸 新築工事 前回の投稿から大分時間が開いてしまいましたが、小さな新築工事の話です。 基礎工事から始まり、柱を立て、屋根を作り、外装、内装を仕上げていきます。 柱だけの状態や、外壁を張る前の状態を写真に撮っていないので、いつも写真が少ないなと思いつつ、現場に行くと写真を撮ることを忘れてしまいます。 いつも見慣れすぎていてどこを撮ればいいかわからない、という事もあります。 小さな新築でも、たくさんの方が関わる事は変わりません。僕一人ではどれだけ時間があっても、どれだけよい道具があっても良い家はできません。 見上げるほど大きな二階建てのお家を小さな新築というのは少し疑問かもしれませんが、昔に比べると今の住宅はどんどん小さくなってきています。 どちらがいいとも言い切れませんが、どちらにせよ良い家を目指し作っていくことには変わりありません。 実はまだ中が少し終わっていませんが、もうちょっとだけがんばります。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
養父市 s様邸 窓追加 今回の写真は、窓のない外壁に窓を追加する工事です。 上の写真の向こうの部屋は、昼間でも照明が必要なほど暗い部屋でした。 この部屋を明るくするために、壁に穴をあけ、窓を追加しようとおもいます。 内側の壁は新しくしましたが、外側の壁はできるだけさわらずに工事をしたいと思っていました。 下の画像が同じ場所に窓を追加した写真です。 少し大掛かりな工事に見えますが、外壁を切ってから窓を付けるまで1日で行っています。 いろいろ必要な条件はありますが、やはり日の光が入ると部屋の中はとても気持ち良くなるので、検討して、できるだけしてみたい工事ではあります。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
養父市 m様邸 廊下工事
チークとは、世界3大銘木の一つにも挙げられる、美しい木材です。深みのある赤みがかった色合いは美しく、強度もあり、硬く、傷がつきにくい材料です。 高価な家具に使われることもあり、ちょっと高級木材でもあります。 すぐ横に大きな窓がある場所で、一般的なベニヤの床板を使うと、すぐ日焼けして表面がべりべりめくれてきたりするのですが、無垢の木の床板の場合は、表面だけめくれるようなことはなく、色の変化も、味わいのある変化となって楽しむことができます。 廊下にチークはもったいないとみるか、日焼けしてすぐに傷む床板より予防の意味を込めてちょっといい床材にすべきとみるか、ちょっと考えて選んでいただきたいポイントの一つです。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
こんにちは、大工の柏尾です。 今回の写真は、養父市M様邸 冊子入れ替え工事です。 既存の冊子をとりはずし、新しいものに取り換えます。 傷めた外壁は、鉄板で隠します。これは防水も兼ねています。 冊子を取り外すために切り取る事になる外壁は、できるだけ小さくなるようにしているので、小さすぎて塞ぐときにちょっとした悩みの種でした。 『この小さい部分を隠すために外壁材を一束頼むのか・・・?』といった感じでした。 今の所は、ちょうどいい大きさの鉄板を見つけたので、鉄板を冊子周りに貼り付けるのがきれいな仕上がり方かな?と考えています。
Comment(0)Trackback(0)
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています
62件中(1件〜10件を表示しています)
前
| 次 |
||||